はじめに
この本を読む動機:
締め切りが重なり徹夜が続くことがあった。なるべく多くの仕事をしたいが、でも徹夜を連続で続けることは避けたい、という思いからこの本を手に取った。
私はキャパシティの上限値が低いため、二つでも仕事が重なるとすぐにキャパオーバーになりやすい。
この本から何を得たいか:
タイトルどおり、徹夜しないでも多くの仕事を回せるようになる方法を知りたい。
読んだ結果:
漫画の原稿作業を夜型から朝型に変えたらアシスタントさんたちの健康が維持され、辞めることがなくなった。そのことで技術も蓄積され、作業効率が2倍に上がったという主旨であった。
作業が大変な資料収集や読み込みなども、編集者にお願いして分担しているという。
著者は漫画家であるので、アシスタントさんや編集者とチームで仕事をすることが前提となっている。
なので一人ブラック自営業になりやすい私の状況とを一概に比較することはできない。
取り入れられるところがあるとすれば、朝型に変えて健康な生活リズムを送ること、だろうか…。
朝は頭が働かず、定時に起きたとしても必ず正午前後にお昼寝を入れないと疲れてしまう。
そう、体力がない。
この問題の場合、スケジュール管理や効率といった技術面よりも、むしろ仕事をこなすための体力やエネルギー維持について考えた方が良いのかもしれない。
この点について何か解決できそうな本を探しておこう。
欲しかった情報はあまり得られなかったが、次の課題が見えたので良しとしよう。
また、漫画づくりにおいていい視点が得られたので以下にメモ。
気になった内容
4章 面白い企画を支える針の穴理論
著者は漫画の企画を考えるときに、大きなテーマからではなく、小さなテーマから始める。
例えば戦争モノをテーマとした場合、「戦争とはいかに悲惨なものであるか」という大きなテーマから始めると、漠然とした内容が出来上がるのだという。
著者は「針の穴理論」といって、大風呂敷を広げるのではなくて、針の穴のように、狭く絞り込んで具体的な疑問を元にテーマを考えるとのこと。
確かに視座を足もとに落として企画を考えると、人物像も定まりやすい気がする。
5章 成功するには、あえて空席を狙え!
世間一般の風潮の反対が「空席」となることがある。
言いたくても言えないことを描くことで、よくぞ言ってくれた!と読者の共感が得られるとのこと。
6章 ストーリーとは、「対立」とその「解決」である
空席を探し、針の穴理論でテーマを考えたら、次は対立の構造を作り出す段階だ。
「世の中の人は喧嘩が大好き」で、世の中の面白いものはほとんど対立でできているという。
親子、兄弟、恋人、学校、会社と、人間関係があるところすべてに対立が起こりうる。
会社の噂話、上司の派閥争い、出世競争、親子喧嘩、ライバル同士の戦いなど、どういう関係の人々が、どういう価値観の違いで対立するのか。
そして主人公がその対立をどう乗り越え解決していくかがストーリーを作るうえで重要だ。
他にも有益な内容があったが、このあたりでメモを止めておく。
上記のマンガづくりのコツ、自身の創作漫画を作るうえでも十分に参考にしたい。
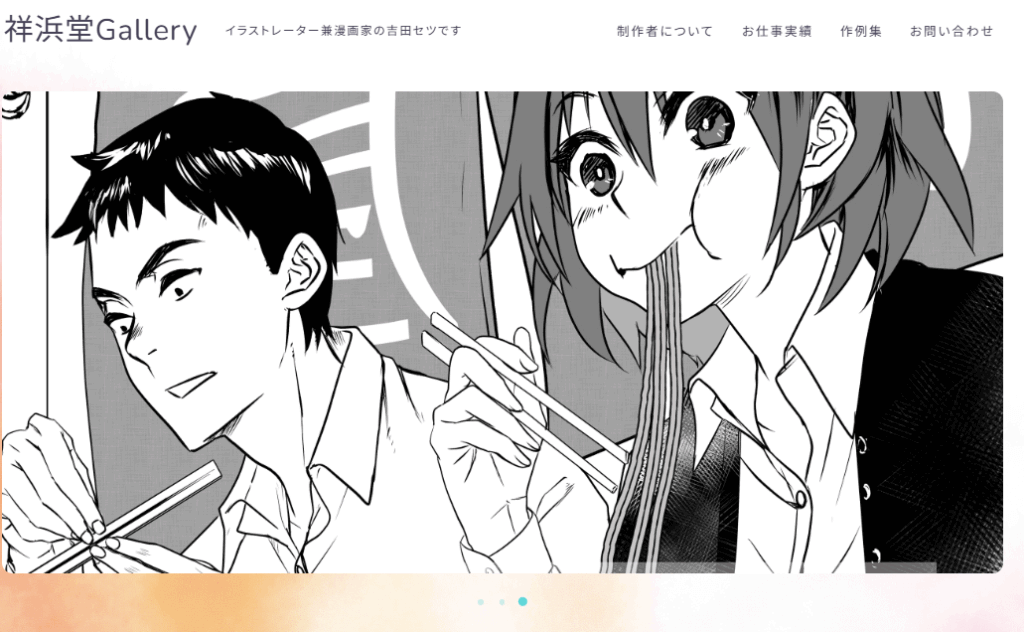
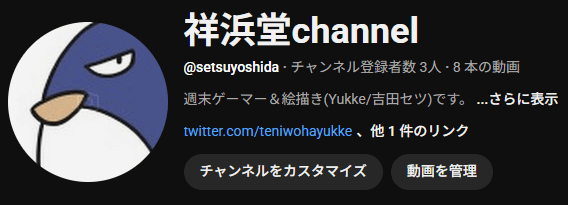
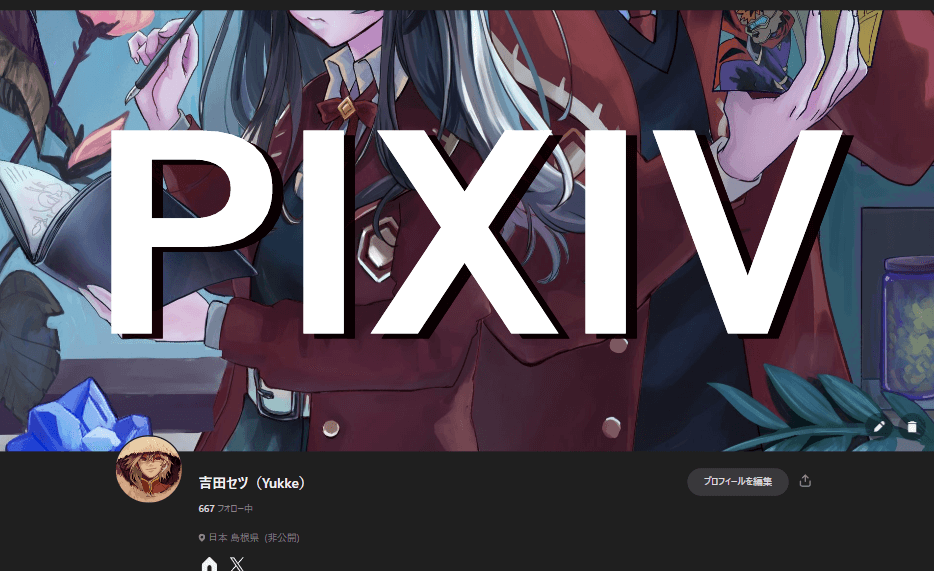

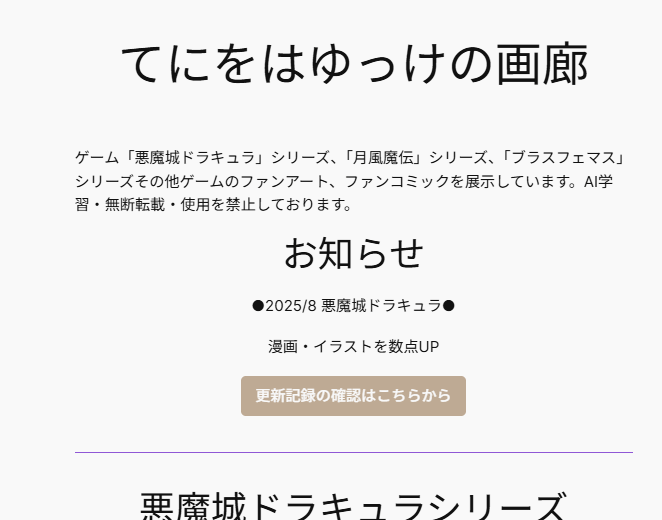


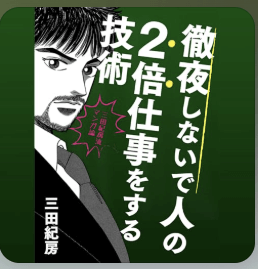
コメントを残す